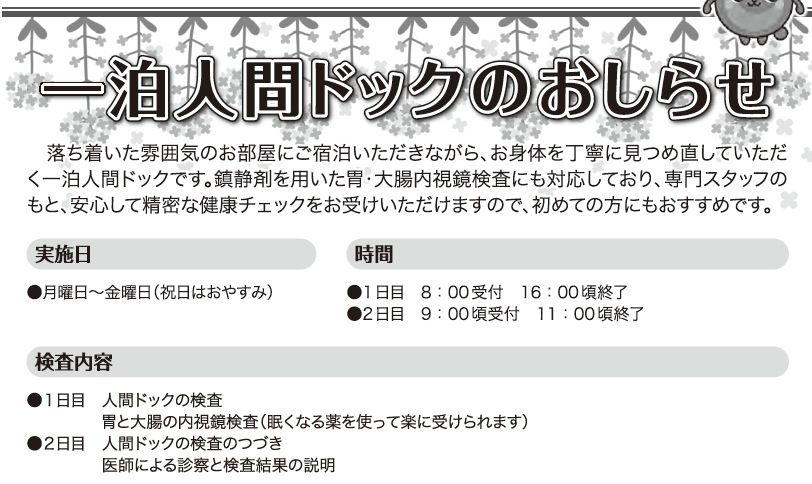大阪府がん診療拠点病院
臨床研修指定病院
紹介受診重点医療機関


【病院】入院・お見舞い方(nyuin/index.html)
入院・お見舞い
【病院】人間ドック(dock/index.html)
健診
人間ドック
外来受診について

当院の特長
当院の特長
FEATURE 01
総合病院ならではの
チーム医療を実践

FEATURE 02
手術支援ロボットによる
高度医療の提供

FEATURE 03
幅広い小児領域の
診療を提供

FEATURE 04
自然な出産、母乳育児など
ママの出産を応援
お知らせ
一覧へ-
広報誌
PL病院ニュース2026年3月号(一泊人間ドック) -
イベント
ぴ~えるサロン案内 -
広報誌
とぅもろー2026年冬号 -
広報誌
PL病院ニュース2026年2月号(小児科 アレルギー外来)
-
患者さま
PL病院を装った不審なショートメッセージ等にご注意ください -
患者さま
近鉄バス 年末ダイヤのお知らせ -
患者さま
アピアランスケアのお知らせ -
患者さま
産婦人科紹介動画をアップしました~家族と迎える安心の出産~
新着情報はありません。
-
イベント
ぴ~えるサロン案内 -
イベント
ボランティアコンサート(オカリナのピース) 10/24(金) -
イベント
ボランティアコンサート(にじのわ) 10/29(水) -
イベント
ぴ~えるサロン案内
-
メディア掲載情報
読売新聞掲載 -
メディア掲載情報
読売新聞掲載 -
メディア掲載情報
読売新聞掲載 -
メディア掲載情報
金剛コミュニティ(2024.10.24発行)